みなみです。
大は小を兼ねるっていうことわざがあります。
大きいものはそれ自体の役割の他に、小さいものの代わりとしての役目も果たすが、小さいもは大きいものの代わりにはならない。
小さいものより大きいもののほうが、幅広く役に立つということ。
故事ことわざ辞典より
お鍋とか、入れ物については確かに大きいものは小さいものの代わりになります。
コップとか、食器も。
冷蔵庫とか洗濯機とかもそうです。
上記のことわざ辞典では車を例に挙げています。
こう言われるとやっぱり大きいものが小さいものより良さそうな気がします。
だからといって、大きいものの方がいつでも優れているということではないと思うんです。
あくまでも「兼ねる」ということです。
代わりになりやすいから便利ということです。
小さい方がいいこともある
反対に小さいほうがいいこともありませんか?
大きいと場所を取るからしまえなくなって、出しっぱなしになってしまうこととか。
どうせすぐ使うんだからここに置いておけばいいか、みたいに。
あ、私のことですが。
しまう場所は兼ねてくれません。
バッグも大きいほうがたくさん入って便利です。
でも小さい方がかわいいバッグもあります。
そのかわいさは大きいものでは代わりになりません。
車だって大きい方が何かと便利ですが、小さい方が小回りが効いたり、燃費や維持費を考えると安かったりするので、家族の人数や使用状況によっては小さいほうがいいこともありますね。
お徳用サイズはお得か
それから、これは「大は小を兼ねる」というかどうかわかりませんが、お徳用の消耗品で、特大サイズのものってありますよね。
こんなの
|
|
お徳用は量に対しての値段と比べると安く思えますが、値段自体はもちろん小さい方が安いです。
小さいものを何度も買うのと比べると安いと思います。
でも、使ってみるとそんなに使うペースは早くなかった。
結局使い切るまでに使用期限が過ぎちゃったりなんていうこともあるかもしれません。
これもまた、しまう場所を取ってしまうこともありますからね。
しまう場所は大切です。
業務用とかでよくありますよね。
業務用として使うなら、毎日大量に使うからいいんですが、それを一般の家庭で使うときは、自分の家の使用状況を考えてから買うといいですね。
まとめ
大は小を兼ねるけど、小さいことがいいこともあるということです。
だから、何かを買ったり選ぶときは、簡単に大きい方がいいとは思わずに、ちょっと考えてみましょう。
使う状況を考えて、必要なら大きい方を選んで、そんなに使う場面が思いつかないなら、小さくても十分なんじゃないでしょうか。
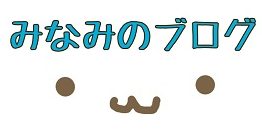




コメント